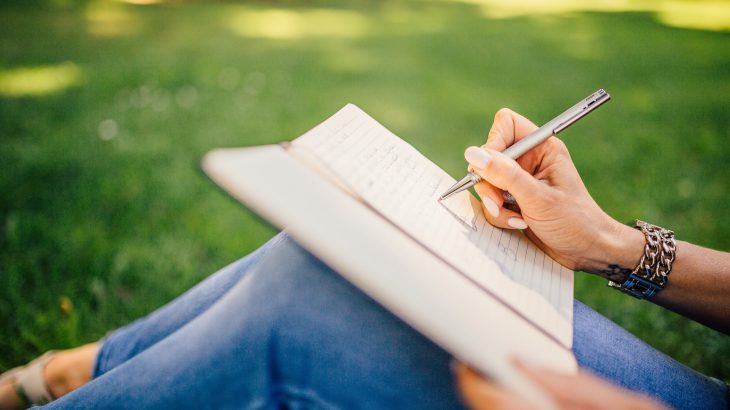9月12日の今日は「宇宙の日」だそう。1992年の今日、毛利衛氏が日本人初のスペースシャトル乗組員として地球を飛び立った日ということで制定されたとのことです。一般人が、手の届く範囲の金額で宇宙へと出かける日が来るのは、あと何年後でしょうかねぇ…。
さて、宇宙とは全く関係のない今日の気になった記事はこちら。
いまは社内のWEB担当としてサイトの運用をしていますが、まだまだ実際の実務についての知識は乏しく、またお客様の理解も進んでいません。この状態でサイトへ記載する文章を書くと、「分かってない新人が書いた、どこかで見たことのあるようなありがちな文章」に大体なってしまいます。すると、お客さんには気づかれます。この会社、中身がないな、どんな会社なのかよくわからないな、と。
元々WEB制作を主業としてやっていたときもそうですが、実際にサイトへ記載する内容は、一番その仕事やお客様のことを理解している人に書いてもらうのが一番です。そのほうが、確実にお客様の心に響きます。会社の色も確実に出ます。
ということで、当時も、今も、できるだけ実務に長く携わっている、仕事のこともお客様のこともわかっていて、自社の特色やどんな思いでその事業をやっているのか、といったことをちゃんと理解しているであろう人(大概は営業の方。なぜなら、普段からお客様へそういったことを伝えることで仕事を取ってきているはずだから)に「書いてください」とお願いするのですが、今までちゃんと書いてきてくれた人はほとんどいません。
以前携わった、100人規模の企業では、サービスマンの方が理解してくれて、短いながらもお客様が知りたくなるような話題について20記事ほど書いてくれました。日本語的に読みやすくアレンジしたあとでそちらをアップしたのですが、数か月後からアクセス数が激増。現在でも、その会社の主要な商品カテゴリ名での検索で1位を維持しています。地方の、小さな企業のサイトが、です。実際に、問い合わせ数も増えていると(当時の話ですが)いうことでした。
文章が(上手、下手に関わらず)かける人と書けない人というのは確実に存在していて、書ける人から見ると「なぜ書けないのだろう」と疑問に思うわけです。そのときに、書ける人からすると「何を書けばいいか分からないからだな」としか思えず、「何を書くかは、こうやって発想しましょう」という教え方になってしまうのでしょう。
ところが、そもそも「文章を書く」ということができない、という人も相当数いて、そういった人は「何を書くか」以前の問題なのじゃないか、ということが上記の記事で書かれています。そして、そういった人たちには、「何を書くか」以前にまず「文章を書く」ことの訓練が必要なのではないか、と。
実は自分自身を振り返ると、小学生の頃、学校の宿題で良く出された「全文書き取り」が非常に好きで、宿題ではなくても、ときどき自主的にやったりもしていました(他の宿題は、割と放ってましたが(^^;))。文章を書くことにあまり抵抗がない理由なのかもしれません(上手いかどうかはともか)。読書なども大事ですが、そもそも文章を書く、という行為自体を訓練することが必要なのではないか、とこの記事を読んで思いました。
実際、絵を描くにしても、まずは好きな漫画の絵などの模倣から始まりますよね。それと同じで、文章を書く訓練としても、まず模倣から始めるのがいいのではないか、と思った次第です。それこそ、好きな小説などを模倣するのは、非常に良い気がします。
これからの時代、特にWEBをどんどん活用していこうという場合は、「文章を書ける」という能力は非常に重宝されるのではないかと思います。今でも、本当に実力のあるライターさんは、様々なシーンで重宝がられています。文章を書くことが苦手という人は、大人でも“模倣”から始めてみると、案外抵抗がなくなる気がします。